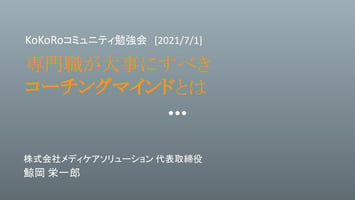【 いよいよ新書籍出版情報、解禁!! 】
コーチングで病院が変わった?ー院内でコーチングを展開していくには
最近、こちらの書籍、「コーチングで病院が変わった」を読み、なるほどな〜・・と感心・感銘を受けていた。

まさにこれは、院長や理事長のようなトップのための書。
特に昨今言われている「医師の働き方改革」を目指すために、全国の医師が養成機関で専門的にコーチングを学び、院内でどのように実践していったか、という具体事例によって構成されている。
思えば、私自身も、2007年(!)〜2009年まで、coach21(→CoachA)→現コーチ・エィ・アカデミアにおいて、専門的に学び、当時 認定プロフェッショナルコーチの資格まで取得した。
私と同時期もそうだし、それ以降も、多くの医療従事者がコーチとなったのを知っているし、現在も他の養成機関含め、看護師やリハ関係など、多くのコーチがいることを知っている。
そんな医療系コーチたちが真っ先に思うのは、自分たちの職場(病院・クリニック)の改革ではないだろうか。この素晴らしいコーチングというものを、自分の組織に広めたい!と。熱い思いで。
しかし、一方で多くの人たちが、現実に直面し、挫折したと思う笑 ハッキリ言って、「1人ではどうにもならない」、と・・・
結論を言うと、やはり、最も重要なのは、経営・トップ陣なのだ。そのレベルでの理解・コミット・号令が無ければ、それはいかんともし難い。
一介のスタッフが、まずコーチングとは何たるかを上司・上層部にプレゼンし、勉強会を開いて、他部署管理者にも理解を仰ぎ・・と、気が遠くなりそうだ笑
この本でも紹介されていたが、管理職にコースに通わせて、院内コーチを何人も養成するなど、やっぱりやることが違うよな、と。
土台、コーチングができる人の頭数。そこまでしないと、せっかくのスキルやマインドも、人数や部署も多く、浸透などしようがない。
しかしよくよく読むと、結局のところ、「人の話をじっくり聴くこと」「やっぱり密なコミュニケーションて大事ですよね」といった、本当に基本のキのことを展開してるにすぎなかったりする。
なぜに今?!という気がしないでもないが汗、
それがちょうど時期的にもコロナ禍であったり、医師の働き方改革だったりとちょうど合致したのだろう。
また、今までだととかく院内の看護・コメディカルでは展開していくが、先生方は度外視、ということが多かったが、医師が率先してコーチングの良さを知り、広めていこうとしているのが大きい。
こちら、ときわ会常磐病院さんや、茨城西南医療センター病院さん、総合南東北病院さんなどがまさにそうだが、トップならびに教育委員会レベルのコミットと明確な意図が不可欠となってくる。
非常に読みやすく、また腑に落ちやすく構成してある本なので、ぜひ院内でコーチング風土を広めるとはどういうことなのか、興味がある方は、紐解いてみてはいかがだろうか。
地域で生き残る、まさに「エクセレントな」病院(施設)を目指して!!